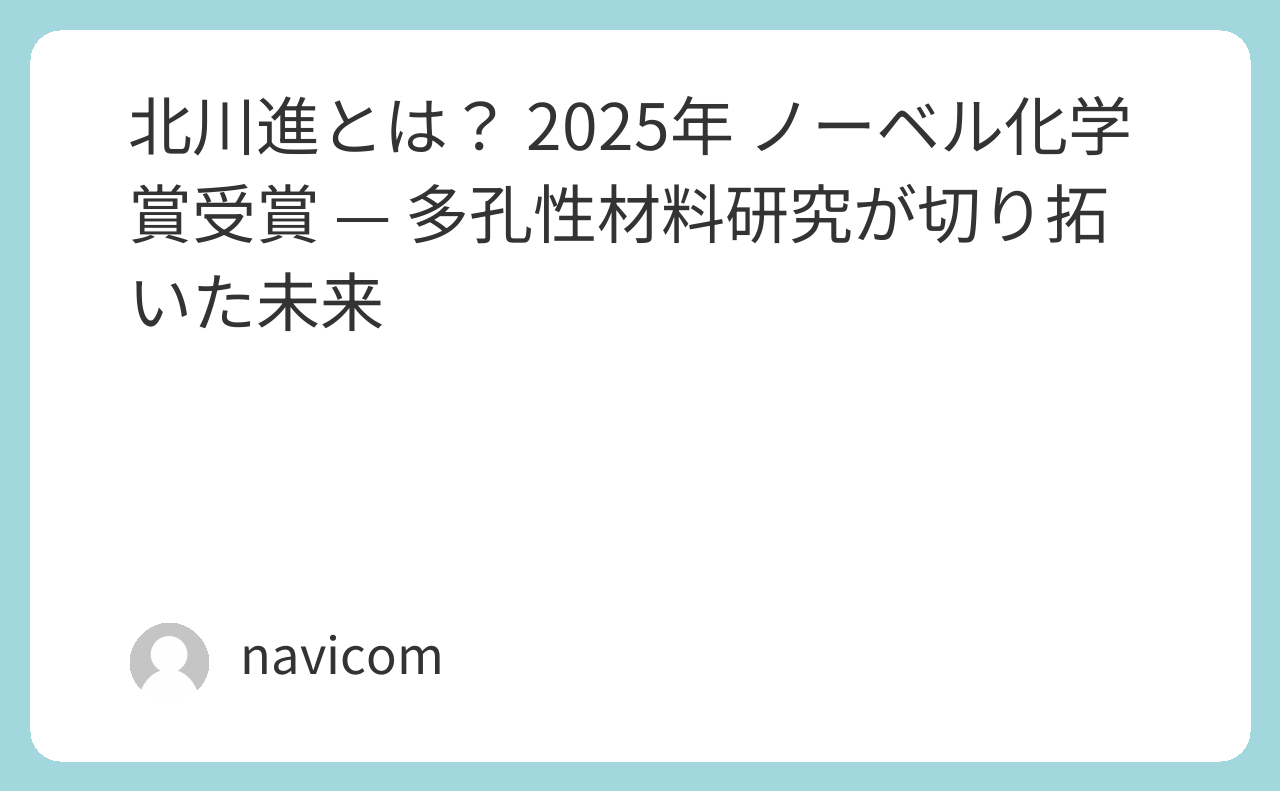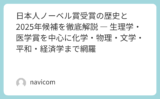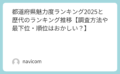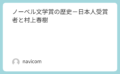2025年10月8日、スウェーデン・王立科学アカデミーは、京都大学・北川進 特別教授を含む 3 名に ノーベル化学賞 を授与すると発表しました。

坂口志文氏のノーベル生理学・医学賞に続く、2025年の日本人2人目の快挙だね!すごい!
受賞理由は、「金属‐有機構造体(MOF:Metal-Organic Frameworks、多孔性材料)の開発」への貢献。
本稿では、まずこの受賞の「なぜ」「どう評価されたか」に焦点を置きつつ、北川進とはどのような研究者か、その研究テーマやこれまでの歩み、そして日本人のノーベル化学賞の歴史的背景にも光を当てます。読者の皆様には、最先端の化学研究がどのように社会とつながるかを感じていただきたいと思います。
北川進先生のご著書はこちら!
日本の歴代ノーベル賞について詳しくまとめた記事はこちら!
1. ノーベル化学賞受賞の概要
発表と受賞者構成
- 2025年10月8日、王立科学アカデミーは 北川進(Susumu Kitagawa)、Richard Robson、Omar Yaghi の 3 名にノーベル化学賞を授与すると発表しました。CNN.co.jp+4Reuters+4AP News+4
- 北川氏は京都大学所属、他の 2 人はオーストラリア(University of Melbourne)とアメリカ(UC Berkeley)所属です。Reuters Japan+4Reuters+4AP News+4
- 賞金として 1,100 万スウェーデン・クローナが授与されると報じられています。CNN.co.jp+1
- 京都大学側も即座にこの受賞を報じ、「理事・副学長、高等研究院特別教授 北川進 氏がノーベル化学賞を受賞された」旨を大学ニュースとして公開しました。京都大学
意義と反響
この発表は、化学界だけでなく広く社会でも大きな反響を呼んでいます。国内外の報道が相次ぎ、研究者コミュニティや産業界でも期待が膨らんでいます。
なぜこの受賞が注目されるのか。それは「MOF/多孔性構造を扱う化学の飛躍」がこれからの環境・エネルギー分野を変える可能性を秘めているからです。
2. 受賞に至る研究内容と評価点
ノーベル化学賞という大きな栄誉を得た背景には、どのような研究があり、どのような点が評価されたのでしょうか。ここでは、受賞理由・研究内容・評価点を整理します。
2.1 受賞理由(王立科学アカデミーの声明・報道ベース)
- ノーベル委員会は、「金属‐有機構造体(MOF、多孔性金属有機構造体)」の開発に対して賞を授与すると発表しました。Reuters Japan+4Reuters+4AP News+4
- これらの材料は、中に大きな空隙を持ち、「ゲスト分子」が出入りできるような構造を持っており、分子を吸着・放出できる能力を備えています。Reuters Japan+4Reuters+4AP News+4
- 委員会はこのような材料を「分子ホテル(molecular hotels)」にたとえ、小さな量で多くの分子を収容できる点を評価しました。Reuters+2The Washington Post+2
- また、受賞理由には「化学者に対して新たな手法を提供した」「世界が直面する環境・資源問題への応用が見込まれる」といった点も含まれています。The Economic Times+3AP News+3Reuters+3
2.2 研究内容と主要な概念
以下は、受賞対象となった研究を理解するための主要なキーワードとその意味を整理したものです。
| 用語 | 概要 | 重要性・受賞との関係 |
|---|---|---|
| MOF(Metal-Organic Frameworks) | 金属イオン(節点)と有機配位子(リンク)を結合させて作る結晶性多孔構造 | 高い空隙率を持ち、ガス吸着・分離・貯蔵・触媒場として有用 |
| 多孔性材料 | 内部に微細な孔(ポア)を持つ固体材料 | 分子の吸着や拡散を制御できる場として利用可能 |
| ゲスト/ホスト相互作用 | 多孔材料(ホスト)と吸着分子(ゲスト)の相互作用 | 吸着選択性、放出制御などを可能にする設計対象 |
| 構造可変性・柔軟性 | 外部刺激(圧力、温度、ガス濃度変化など)で構造変化する性質 | 応答性材料としての可能性を開く |
| 設計可能性 | 金属、配位子、結晶構造を変えることで目的性能を設計できること | 多様な用途・応用を生み出す鍵 |
北川教授・共同受賞者らは、上記のような構造設計思想と手法を発展させ、分子挙動を制御できる MOF の設計と創成において顕著な成果を挙げました。
2.3 評価された点・技術革新
複数の報道やノーベル発表を通じて明らかな評価点を以下にまとめます:
- 新しい分子アーキテクチャの創出
従来の材料では困難だった「大きな空隙を持つ結晶構造」を自在に設計・合成する道を切り開いた点。Reuters+2The Washington Post+2 - 応用可能性と課題対応力
水の収穫(乾燥地帯の空気中から水を引き出す)、CO₂ 回収、有害ガスの貯蔵、触媒反応場など、現実の社会課題とつながる用途が期待される点。The Washington Post+3Reuters+3AP News+3 - “少量で高機能”の強み
「小さな量でも多くの分子を扱える」点が、材料効率とコスト効率の面で優れていると評価された点。報道では「ハーマイオニーのバッグ」たとえが使われています。ウォール・ストリート・ジャーナル+2The Washington Post+2 - 設計自由度と拡張性
MOF は構成ユニット(金属・配位子)を変えることで無数のバリエーションが可能で、「無限の設計可能性」を持つという点。The Washington Post+2Reuters+2 - 化学者に新たな道具を提供
受賞発表では、「化学者に化学を解く新しい機会を与えた」と述べられており、材料設計という分野の枠を広げた点も強調されています。AP News+2Reuters+2
こうした点が評価され、ノーベル賞受賞につながったと考えられます。
3. 共受賞者と世界の化学賞動向
ノーベル化学賞は単独授賞、または複数名での授賞が一般的です。今回の受賞者および過去の動向を見ておきましょう。
共受賞者:Richard Robson / Omar Yaghi
- Richard Robson(University of Melbourne)
MOF 分野の先行研究者として知られ、構造設計法・結晶工学の分野で長年貢献。Reuters+2ウォール・ストリート・ジャーナル+2 - Omar Yaghi(University of California, Berkeley)
MOF 研究界で広く知られる研究者で、多孔性構造の先駆的報告・応用展開で多数の成果を持つ。The Economic Times+4AP News+4Reuters+4
彼ら 3 人はそれぞれ独立して研究を重ねつつも、MOF 分野における貢献度が互いに補完的・発展的であったため、共受賞という形になりました。
世界の化学賞受賞傾向と MOF に対する評価
- 過去のノーベル化学賞では、有機合成、触媒、分子機能、材料化学、生体分子解析などが受賞対象になってきました。
- 最近の化学賞は、「分野をまたぐ融合」「実社会への応用性」 を強く意識されたテーマが目立ちます。
- MOF/材料設計は、従来の無機化学・材料科学・触媒科学などを横断するテーマであり、今回の受賞はその流れの象徴とも言えます。
4. 日本人のノーベル化学賞受賞史と背景
北川氏の受賞を単なる「個人の栄誉」として見るだけでなく、日本という国・研究基盤の文脈でみると、より興味深い背景が見えてきます。
日本人の化学賞受賞者一覧と業績
公益社団法人日本化学会は、以下のように日本人のノーベル化学賞受賞者を整理しています:日本化学会
| 受賞年 | 受賞者 | 受賞理由概要 |
|---|---|---|
| 1981 | 福井 謙一 | 化学反応過程に関する理論的研究(フロンティア軌道理論など) |
| 2000 | 白川 英樹 | 導電性高分子の発見と開発 |
| 2001 | 野依 良治 | 不斉触媒による水素化反応 |
| 2002 | 田中 耕一 | 生体高分子の同定・構造解析手法(質量分析法等) |
| 2008 | 下村 脩 | 緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見と応用 |
| 2010 | 鈴木 章 | 有機合成におけるパラジウム触媒―クロスカップリング反応 |
| 2010 | 根岸 英一 | 有機化学における触媒開発(クロスカップリング反応) |
| 2019 | 吉野 彰 | リチウムイオン電池の基盤材料開発 |
このように、北川進氏は、この流れに新たな名を加える形になります。京都大学+4日本化学会+4Nippon+4
京都大学のサイトでも、北川氏の受賞を大学の歴史上の栄誉の一つとして誇り高く伝えています。京都大学+1
背景と意義
- 化学分野での世界的競争
化学という学問分野は、多様なサブ分野(無機化学、有機化学、高分子化学、生化学、材料化学など)を包含しており、日本の研究者が世界をリードするには、それぞれの分野で国際的な競争力と基盤支援が必要です。 - 基盤研究支援の確保
ノーベル賞受賞者が出る背景には、長期にわたる基礎研究支援、研究資金確保、国際共同研究体制、若手育成などが不可欠です。日本国内でも研究基盤強化の議論が繰り返されてきましたが、今回の受賞はその努力の成果として象徴的意義を持つ可能性があります。 - 後進への刺激・発信力
ノーベル賞受賞は、国内外メディアで大きく取り上げられ、研究分野への注目を呼び、若手研究者や学生へのモチベーションを高める効果があります。 - 応用研究との接続
日本では材料・化学分野の応用技術(半導体、電池、触媒など)が産業と結びついてきた歴史があり、MOF のような最先端材料は、将来産業化への道筋をもたらす可能性があります。
こうした流れ・背景の中で、北川氏の受賞は日本科学界にとっても象徴的な出来事と言えるでしょう。
5. 北川進とは誰か:略歴・所属・研究テーマ
ノーベル賞受賞者としての顔とともに、北川進という人がどのようなキャリアを歩んできたかを整理します。
略歴・役職(要約)
以下は、公開されている情報をもとにした略歴の整理です:
| 年代 | 主な所属・役割 |
|---|---|
| 1974 | 京都大学 卒業 |
| 1979 | 京都大学 博士号取得 |
| 1980~1990 年代 | 近畿大学、東京都立大学(あるいはそれに準ずる組織)で教職を経験 |
| 1998~ | 京都大学 教授・研究者として本格的に活動 |
| 過去 | iCeMS 拠点長、副拠点長、KUIAS 所属など複数の研究拠点運営に関与 |
| 現在 | 京都大学 高等研究院 特別教授、理事・副学長(研究推進担当)など |
| 2025 年 | ノーベル化学賞受賞、多孔性材料研究の第一人者として国際的評価を確定 |
京都大学の公式発表では、北川進 理事・副学長、高等研究院特別教授 の肩書で受賞報道がなされています。京都大学
研究テーマ・専門分野
北川氏の専門分野・研究テーマは、主に次のようなキーワードで語られます:
- 無機化学 / 配位化学
- 多孔性材料(MOF、PCP:配位高分子)
- 構造制御・設計化学
- 応答性材料・可変構造材料
- 分子吸着・分離・貯蔵・触媒応用
特に「配位空間の化学」と呼ばれる、分子を受け入れる空間を自由に設計・制御する思想が、北川氏の研究を特徴づけています。
6. 北川研究の特色と研究室風景
ノーベル賞受賞に至る研究は、個人のセンスだけでなく、研究室・環境・ネットワークがあってこそ実現できるものです。この章では、北川氏の研究室や研究方針、特徴を読みやすく整理します。
6.1 所属拠点・研究組織体制
- 京都大学 高等研究院 / KUIAS:大学横断型先端研究拠点。北川氏はここで特別教授の肩書きを持っています。
- iCeMS(物質–細胞統合システム拠点):材料科学と生命科学の融合を目指す拠点。北川氏は過去に拠点長・副拠点長などを務めた経験があります。
- Kitagawa Group / 北川研究室(KUIAS-iCeMS 所属):合成、構造解析、物性評価、応用検討を統合的に行う研究室。
このような研究インフラと組織支援が、複雑な材料設計を支える基盤となっています。
6.2 研究方針・理念
北川氏の研究室には、いくつか特色ある方針があります:
- 融合型アプローチ:化学、物性、理論解析、シミュレーションを組み合わせて研究を進める。
- 構造 ⇄ 機能 の関係性重視:ただ単にきれいな結晶をつくるのではなく、機能を引き出すために構造をどう制御するかを重視。
- 柔軟性・可変性:刺激応答性(温度、圧力、吸着ガスなど)を持つ変化可能な結晶構造を設計。
- 国際展開:世界中の研究機関との共同研究が活発。学生・ポスドクも国際的な発表機会を得やすい環境。
- 若手育成重視:大学院生・ポスドクの自律性を尊重しつつ、テーマ設定・発表支援を行う体制。
6.3 研究室風景(予想される日常)
実験室での合成作業、X 線回折装置での構造解析、ガス吸着装置での性能評価、理論・シミュレーションとの対話、共同研究ミーティング、学生指導と論文執筆…というサイクルが日常的に回っているでしょう。研究の自由度と共同体的な議論が混ざり合う場面が想像されます。
7. 研究資金・プロジェクトとの関係性
ノーベル級の研究を支えるには、適切な資金とプロジェクト体制が不可欠です。北川氏は、さまざまな研究プロジェクト・助成金を活用しながら、研究展開を進めてきたと推察されます。
主な資金源・プロジェクト例
- 科研費(KAKEN):基盤研究(S/A 等)等を代表者として取得しており、テーマ維持と拡張の基盤。
- JST/ACT-C 等戦略型プロジェクト:応用的な材料設計・技術展開を視野に入れたプロジェクトとの連携実績。
- 拠点形成型研究・組織支援:iCeMS や KUIAS の運営資金、学内補助金、共同研究支援金など。
- 共同研究・企業連携補助金:産業界との共同テーマを進めるための協力金・助成金。
- 国際共同研究助成:海外機関との連携を支える国際助成金や交換プログラム資金。
こうした資金体制を背景に、研究テーマの継続性と拡張性を確保しつつ、新しい挑戦が可能になっています。
8. 社会応用・ベンチャー展開の展望
ノーベル賞受賞研究は、必ずしもすぐに製品化に直結するわけではありません。しかし、北川氏の MOF 研究は、多くの応用可能性を秘めています。
ベンチャー企業・技術移転の動き
- 例えば、株式会社 Atomis(アトミス) は、MOF を基盤技術とした事業展開を目指すスタートアップとして知られています。CNN.co.jp+1
- 研究室 → 特許 → 企業化・共同研究のルートを通じて、MOF 材料を社会で使える形に落とし込む取り組みが続いています。
応用分野・可能性
北川氏の研究方向性と受賞評価から考えると、以下の応用分野が特に期待されます:
- 二酸化炭素の回収・活用
- ガス分離・浄化・貯蔵(例:水素、メタン、CO₂)
- 有害ガス吸着・処理
- 触媒材料・反応場設計
- センサー材料・検出技術
- 水収穫(乾燥地域の空気中から水を取り出す技術)
これらの応用可能性と社会ニーズとの接点が、今後の研究方向を決める大きな指針となるでしょう。
9. 読者にとっての示唆・関心点
この記事をお読みの方は、研究最前線に興味を持つ一般読者だと思います。以下に、少し視点を変えた読みどころを列挙します。
- ノーベル賞受賞研究を通して、「研究とは何か」「科学とは何を目指すか」の一端を感じられる
- MOF のような最先端材料が、環境・エネルギー問題解決にどうつながるかを理解する手がかりに
- 日本の大学・研究機関が世界とどう競い、連携しているかの実例を知る
- 北川進という人物が、研究者として・研究室運営者としてどういう道を歩んできたかを知る
- 今後、ノーベル賞受賞を契機にどのような研究方向・産学連携が進むかに注目できる
10. 結びにかえて
2025年ノーベル化学賞受賞というニュースは、北川進氏の長年の研究努力の結果であるとともに、日本および世界の化学・材料科学界にとって新しい節目となる出来事です。
MOF/多孔性構造材料の設計・制御という分野は、これからさらに応用展開が期待されます。今回の受賞を機に、これらの研究がより広く社会課題に応える方向へ展開する可能性も大きいでしょう。
今後、受賞を契機とした研究室の動き、共同研究、成果の技術移転、若手研究者の登場などに注目しながら、化学と社会の接点を感じていただければと思います。
(注:本記事は、主要報道・大学公式発表をもとに執筆しています。速報段階の情報については、正式発表・信頼できる報道機関情報を合わせてご確認ください。)