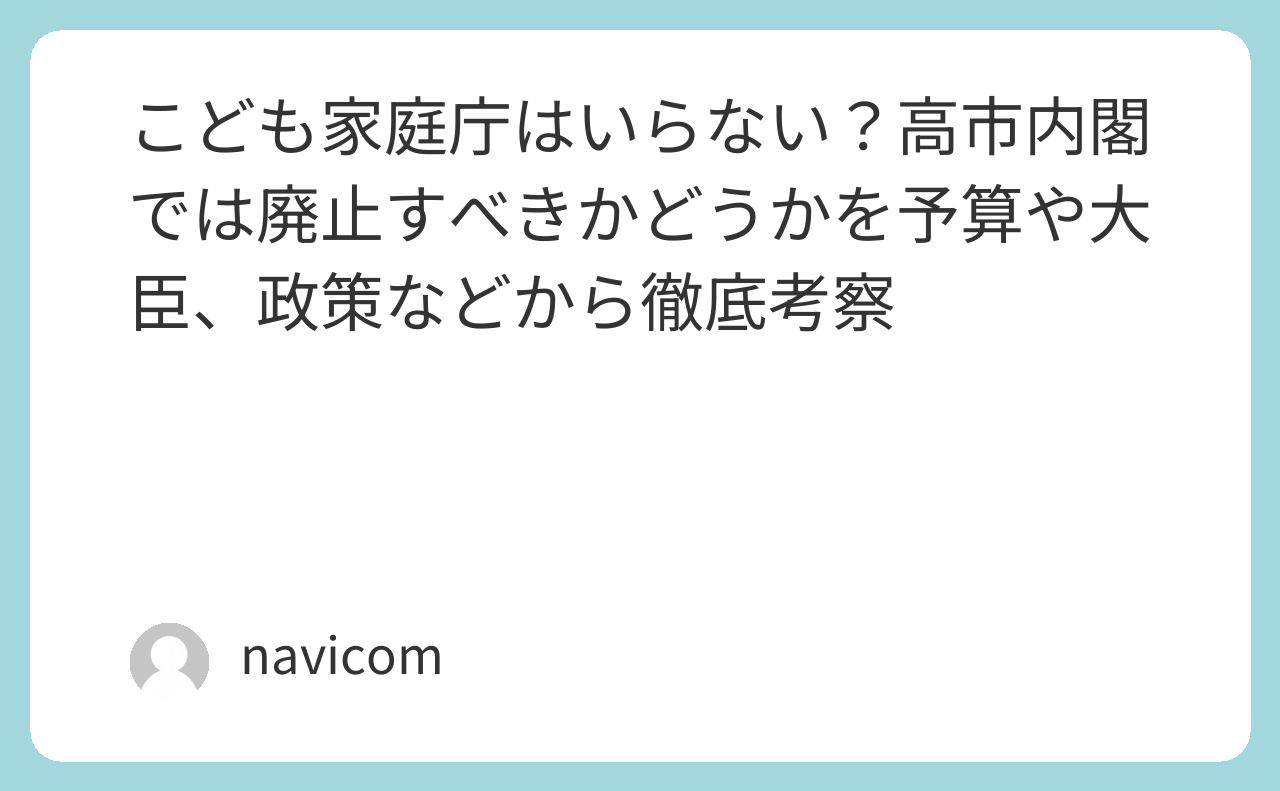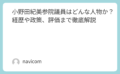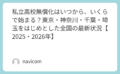序章:議論の背景 — なぜ「こども家庭庁はいらない/廃止論が浮上しているか
少子高齢化、人口減少、子育て世帯の経済的・時間的負担の増大、地域による子育て環境の格差――日本が直面しているこのような課題を背景に、子ども・子育て支援政策は国家的な最重要テーマとされてきました。こうした中で、「子ども・子育て政策の司令塔」を設けるべきだという議論が、長年にわたって政府・与党内で行われてきました。実際、2023年4月に「こども家庭庁」が発足し、子ども・家庭政策を一元化すべく新たな行政機関が誕生しました。
しかし同時に、「本当にこの庁が必要なのか」「コストに見合っているのか」「省庁横断で司令塔として機能しているのか」といった疑問も浮上しています。ネット上には「こども家庭庁 いらない」「子ども家庭庁 廃止しろ」といった言葉も散見されており、議論の中で「存続か廃止か」という構図が見え隠れしています。例えば、「こども家庭庁の予算は“無駄”だ」という批判も報じられています。 東京すくすく+1
さらに、2025年10月に入り、保守強硬派を背景にした新たな政局が動き出しており、高市早苗氏が総裁選に勝利して女性初の首相就任の可能性が指摘されています。これにより「高市内閣」での政策再検討、行政機関の見直しが念頭に置かれ、こども家庭庁の存廃論も改めて注目を集めています。 東洋経済オンライン+1
このような背景のもと、本稿では「こども家庭庁はいらない?高市内閣では廃止すべきかどうか」をテーマとして、予算・大臣・政策・制度の観点から徹底考察を行います。
第一章:こども家庭庁の設立と制度的概要
1-1 設立の経緯
「こども家庭庁」は、政府が少子化克服・子ども・子育て支援の司令塔をめざして設置を決めた行政機関です。政府が2021年12月に閣議決定した基本方針の中でも、「少子化の克服、子どもを産み育てやすい社会の実現」を掲げ、いわゆる子ども子育て政策の司令塔設置に言及していました。 J-STAGE+1
設置法案も国会に提出され、2022年6月に成立。 こうして2023年4月1日付で内閣府の外局として発足しました。 ウィキペディア+1
なお、設立準備段階では「こども庁」という名称案もありましたが、最終的には「こども家庭庁」となりました。名称を巡っても議論がありました。 立憲民主党+1
1-2 組織構成・所管範囲
こども家庭庁の組織は、主に以下の通りです。
- 内閣府特命担当大臣(子ども政策担当)を置き、子ども・子育て政策の指揮権を持ちます。 ウィキペディア+1
- 長官(庁のトップ)および内部の局(成育局・支援局等)を備え、子ども・家庭・子育て支援・虐待防止・障害児支援など、従来省庁にまたがっていた政策を横断的に扱う体制が整えられています。 ウィキペディア+1
- 組織構成資料では、3つの部門「企画立案・総合調整部門(長官官房)」「成育部門(成育局)」「支援部門(支援局)」という構成が紹介されています。 ウィキペディア+1
所管政策範囲としては、幼児・児童の成育基盤整備、保育・放課後児童クラブ、児童手当、育児休業給付、ひとり親家庭・障害児支援、児童虐待防止、子どもの安全・自殺対策など多岐に渡ります。設立の目的として、これらを「縦割り行政・省庁横断の弊害から解放し、子ども政策を“子どもを中心(子どもまんなか)”に一元的に進める」ことが掲げられました。 一般社団法人平和政策研究所+1
1-3 予算・人員規模
当初、設立時の予算・人員も報じられています。ウィキペディアの記述によれば、2023年度には約430人体制、予算額は約3兆9690億円程度とされています。 ウィキペディア
また、最近の報道では、2025年度の予算要求が “約7兆3270億円” とされ、前年度比で約1.1兆円増となっているという分析もあります。 TechGym+1
このように、設立から間もない機関ながらも、かなり巨額な予算規模となっており、国民の税負担・行政効率・成果の観点から批判も浴びています。
第二章:こども家庭庁の実績・課題
2-1 実績・事業内容
こども家庭庁は、子育て支援・少子化対策・児童虐待防止・障害児支援など多様な施策を所管しています。例えば、2025年度の予算内訳をみると、保育所・放課後児童クラブ運営費が約2兆4600億円、児童手当が約2兆1700億円、育児休業等給付が約1兆600億円、といった大きな勘定科目があります。 東京すくすく+1
また、障害児支援・虐待防止支援が約8500億円、大学授業料減免等が約6500億円というデータもあります。 TechGym+1
このように、支援対象・事業範囲は広く、子育てや家庭をめぐる公的支援が体系化される方向にはあると言えます。
2-2 課題・批判点
しかしながら、設立後の実務・運営にはいくつかの大きな課題が指摘されています。
(1)説明責任・会見運営の問題
たとえば、2025年10月17日の閣議後の会見で、当時大臣を務めていた 三原じゅん子氏が「特にご報告はありません」と述べたまま、質疑応答なくわずか27秒で終了したという記事があります。 女性自身
この「報告ゼロ・質問ゼロ」の会見にSNSでは「#こども家庭庁不要」「#税金の無駄遣い」といった反発が拡散されるなど、説明責任の欠如としての批判が噴出しました。 coki
(2)効果実感の乏しさ/少子化の改善が見えない
また、巨額予算を投入しても出生数が理想的に改善していないという指摘があります。例えば、2025年度予算が約7.3兆円に上がったにもかかわらず、出生数70万人割れという見通しも出ています。 TechGym
この「実感が伴わない」という状況が、庁の存在意義に疑問を向ける一因になっています。 note(ノート)
(3)予算の“削れない”構造/冗費の指摘
予算の内訳をみると、子育て支援・保育・給付金といった支出が大部分を占めるため、仮に「庁を廃止して支出を削る」という発想が浮上しても、実務的にはそのまま削減=撤退には繋がりにくい構造となっています。報道では「約7兆円のうち、約77%が保育・学童運営費・児童手当・育児休業給付である」とのデータもあります。 東京すくすく
このため、「庁があるから支出が膨らんだ」「庁があるから冗官が増えた」といった批判構図が出やすくなっています。例えば、設立時から「省庁再編しないなら冗費ではないか」という指摘もありました。 note(ノート)+1
(4)制度・運営の未成熟さと、省庁横断の困難
「子ども政策を一元化する」という設立趣旨であったにもかかわらず、幼稚園や認定こども園の所管が完全に移らなかったり、文部科学省・厚生労働省・内閣府の既存権限との調整が十分でないという論点もあります。 note(ノート)
第三章:存廃論点 ― 「こども家庭庁はいらない/廃止すべきか」
この章では、「廃止すべき」とする立場、「存続・改革すべき」とする立場、それぞれの論拠を整理し、最後にメリット・デメリットを表形式で整理します。
3-1 「廃止すべき」とする主張・論拠
- 巨額予算にもかかわらず成果が見えにくく、説明責任が不十分である。上述のように会見がわずか数十秒とか、実感改善に乏しいという批判があります。
- 「庁を廃止すれば年間7兆円の財源が浮く」といった声もあり、財政負担・行政機構の肥大化への懸念があります。 東京すくすく+1
- 庁新設が新たな省庁・官僚機構・大臣ポストを増やし、利権・冗官化を招いたという指摘もあります。 note(ノート)+1
- 子ども・子育て支援は既存の省庁でも機能するという観点から、むしろ「省庁再編しないなら新庁は無駄」という論点もあります。 note(ノート)
3-2 「存続・改革すべき」とする主張・論拠
- 少子化・子育て支援という国家的課題の重大性を鑑みると、司令塔的機能を有した専門機関があることの意義は大きい。行政横断・家庭政策を包括的に扱える枠組みの必要性が繰り返し指摘されています。 一般社団法人平和政策研究所
- 各種支援(児童手当・保育・学童・障害児支援など)は既に多額の支出をともなっており、これらを統括・調整する機関を廃止すれば、支援の断絶・移管混乱というリスクがあります。先述の通り、支出項目の77%が削減困難な支援項目です。 東京すくすく
- 改革可能な余地を残したまま、機能強化・説明責任の改善を図る方が、廃止よりも現実的かつ効率的であるという見方があります。
3-3 表:メリット/デメリット整理
| 観点 | 廃止すべき場合のメリット | 廃止すべき場合のデメリット | 存続・改革すべき場合のメリット | 存続・改革すべき場合のデメリット |
|---|---|---|---|---|
| 財政・コスト | 機関維持コスト・冗官を削減し、財源の見直しが可能 | 支援削減・制度移管に伴う混乱・負荷増 | 専門機関を維持することで子育て支援の一貫性・司令塔機能を確保 | 機関維持自体がコスト重・廃止論を招く可能性 |
| 制度統一性・実効性 | 既存省庁に統合すれば重複をなくせる可能性 | 支援体制の切り替え・政策の分断リスク | 横断的・長期的に子ども支援を統括できる | 現状機能未成熟・成果が見えにくく、逆に信頼を損なう可能性 |
| 説明責任・透明性 | 廃止を機に見直し・縮減を明確にできる | 撤退による国民説明責任・影響の説明が難しい | 機関を改革し説明責任を強化すれば信頼改善の機会 | 改革が遅れれば「存続のためだけ」化する恐れ |
| 少子化・家庭支援政策 | 支援の重点を再配分し“現場重視”にシフト可能 | 新設庁での統一政策が崩れ、支援がばらつく可能性 | 少子化・家庭支援を国家レベルで位置づけ維持できる | 少子化改善が見えなければ政策不信につながる |
第四章:政治・大臣・政権との関係
4-1 歴代大臣・長官の状況
「こども家庭庁 大臣 歴代」「子ども家庭庁 大臣 加藤鮎子」「三原じゅん子 こども家庭庁 大臣」などのキーワードがありますが、整理します。
設置時からこの庁に付随する大臣ポスト・長官ポストがあり、例として長官は初代が約430人規模の体制であるとウィキペディア等に記載があります。 ウィキペディア
ただし、最近の報道では「三原じゅん子こども家庭庁大臣」が注目されており、会見のあり方などで批判されています。 女性自身
また、政党側・野党側では設置時から反対意見もあり、例えば 立憲民主党 は、設置法案に対して「理念・実効性に大きな懸念がある」とコメントしています。 立憲民主党
なお、「子ども家庭庁 大臣 高市内閣」「子ども家庭庁 大臣 高市早苗」といったキーワードもありますが、2025年10月時点では、総裁選で高市早苗氏が総裁になる見込みという報道が出ており、内閣改造・新大臣就任も視野に入っています。 東洋経済オンライン+1
4-2 政権交代・大臣交代の影響
2025年10月6日付の記事では、高市早苗氏が自民党総裁選を勝ち抜き、10月15日には初の女性首相就任が見込まれていると報じられています。これにより、政策面では保守色の強い高市氏がどのような少子化対策を掲げるかが注目されています。 東洋経済オンライン
また、同記事では「政権の足元には地雷原が広がっている」「改革課題が多く、短命政権に終わる可能性もある」との記述もあり、新政権下でのこども家庭庁の位置づけ・見直しも予見されています。
さらに、10月15日付の閣僚人事報道で、こども家庭庁等を所管する担当大臣として、黄川田仁志氏が起用された旨が報じられています。記事では「地方創生やこども家庭庁など非常に所管が多く身の引き締まる思いだ」と述べており、新体制下での少子化・子育て政策の展開に注目が集まっています。 アメーバブログ(アメブロ)
このように、政権・大臣の交代や人事により、こども家庭庁の政策の方向性・存廃議論ともに変化が起きる可能性があります。
4-3 高市内閣(仮称)における議題
「高市内閣」「高市早苗」といったキーワードが示す通り、保守色の強い高市政権への移行が目前に迫っており、少子化・子育て支援政策の改革期待とともに、既存機関・庁の見直しも議論されています。高市氏自身は政調会長時代に「ベビーシッター代・家事代行サービスに税額控除を導入すべき」といった提言もしており、従来の給付型支援から転換を模索する姿勢も垣間見えます。 note(ノート)
このため、「こども家庭庁 廃止 政党」「こども家庭庁 解体」「こども家庭庁 省庁統合」といった議論も高市政権下で浮上する可能性があります。
第五章:予算・財源観点からの考察
5-1 年次予算額・推移
先にも触れた通り、こども家庭庁の予算規模は着実に膨らんでおり、最新の分析では以下のようになっています。
- 2025年度予算:約7兆3270億円(前年度比+約1.1兆円) TechGym+1
- 概算要求:2026年度に向けては約7兆4229億円という数字も報じられています。 東京すくすく
予算内訳としては、保育所・放課後児童クラブ運営費約2兆4600億円、児童手当約2兆1700億円、育児休業等給付約1兆600億円、障害児・虐待防止等約8500億円、大学授業料減免等約6500億円。 TechGym+1
5-2 費用対効果・財源確保の観点
このような巨額の予算を投入しているにもかかわらず、「実感が得られない」「少子化が止まらない」「支援の届きにくさがある」といった批判が出ています。つまり、投入額に対する「成果の見える化」が十分でないという課題です。
さらに、庁維持そのものにかかるコスト、官僚機構・大臣ポスト・組織運営の費用も見逃せません。また、予算の大半が既に「保育・手当・給付」という年度内消費型の支出に充てられており、新規政策・構造改革に回せる余地が少ないという構図もあります。保育・学童などの維持支出が全体の約77%を占めるという分析もあります。 東京すくすく
5-3 廃止・縮小した場合に生じる影響
もし「庁を廃止」または「統合・縮小」する場合、以下のような影響が考えられます。
- 支援事業(手当・保育・学童・育児休業給付など)の所管が既存省庁に戻された場合、移管コスト・混乱が予想されます。
- 財源配分の再検討が必要となるため、支援対象者・地域間格差・給付水準の見直しが伴う可能性があります。
- 廃止を口にしただけで「支援削減」「子育て軽視」という批判を受けるリスクがあります。
- 一方、冗官・官僚拡充・組織肥大化という批判には対応できますが、支援の実務維持という観点からは慎重な判断が必要です。
第六章:政策・制度観点からの考察
6-1 こども家庭庁が掲げるビジョン・施策
こども家庭庁の重要な政策理念として、「子どもまんなか」「こども・家庭・地域を基盤とする社会づくり」「子どもの権利条約の4つの原則を踏まえた施策推進」などが挙げられています。 (キーワード:子どもの権利条約 4つの原則)
また、「3つの柱」や「3つの部門」という構成も公式に掲げられており、例えば成育基盤強化・家庭支援・地域支援という観点から政策展開が図られています。これに加え、障害児支援・児童虐待防止・子育て世帯支援・大学授業料減免など、施策の幅は広がっています。
6-2 廃止・移管シナリオの具体論
「こども家庭庁 廃止 政党」「こども家庭庁 解体」といった議論がネット上・署名運動でも出ています。たとえば、Change.org上には「こども家庭庁の解体を求める署名」があり、「税金の無駄遣い」「現場支援が希薄」といった主張が記されています。 Change.org
また、X(旧Twitter)上でも「こども家庭庁をなくせば財源確保できる」といった投稿が目立っています。 X (formerly Twitter)
ただし、制度的観点からは、既存省庁(厚生労働省・文部科学省 等)に丸ごと移管すれば縦割り行政の再生・統合効果が期待できますが、新設庁設置の趣旨が無かったことになってしまいます。さらに、実務上、保育所・学童・給付金といった支援は日々実施されており、庁単位の廃止=支援撤退と短絡的に結びつけるのは政策的リスクがあります。
6-3 政党・世論の動き
具体的には、立憲民主党が設置法案に反対したという過去の動きがあります。 立憲民主党
また、世論・ネットでは「子ども家庭庁 いらない 知恵袋」「子ども家庭庁 いらない 署名」といった動きもあり、署名数5,000件超の解体要求運動も報じられています。 Change.org
このように、制度・政治・世論の各側面で、存続・改革・廃止のいずれを選ぶかという争点が存在しています。
結論:私見・提言
本稿で整理してきたように、こども家庭庁は「少子化・子育て支援」という極めて重要な国家課題に対して、横断・総合的に取り組むための行政機関として設立されました。一方で、設立から時間が浅いこと、成果の見えにくさ、説明責任の不十分さ、予算の巨額化・組織の肥大化への懸念など、批判される点も少なくありません。
私見としては、「廃止すべき」という結論には至らず、「存続・改革すべき」という立場を取ります。理由は以下の通りです。
- 少子化・子育て支援は待ったなしの課題であり、既存省庁だけでは縦割り・対応抜け・政策の断絶リスクがあるため、司令塔的機能を有する機関の存在意義は依然高いと考えられる。
- 予算・支援が既に膨大で、即時に「廃止=支援撤退」と捉えられかねないため、国民・対象家庭に対して大きな影響を及ぼすリスクがある。
- しかしながら、現状では機能・説明責任・成果可視化に課題があるため、「そのまま維持」では信頼を損ねる可能性がある。したがって、むしろ「改革強化」こそが必要です。
提言
以下、存続・改革案として提言します。
- 説明責任・透明性強化
大臣会見を定期・質疑応答付きで実施し、予算執行・成果・指標を明示する。わずか数十秒の会見では国民の信頼を得られません。 - 成果指標(KPI)・EBPM(証拠に基づく政策)導入
「出生数」「児童虐待相談件数/対応率」「保育待機児童数」「学童利用率」「障害児支援充実度」等、定量的指標を設定し、毎年度公表。キーワード「EBPM推進室」や「こども家庭庁 EBPM」が今後の行政トレンドです。 - 予算の中身見直し・重点化
既に維持支出となっている給付・保育・学童などの運営費に加えて、「新たな構造改革型支援(例:家事支援税額控除・柔軟な働き方支援)」へのシフトを検討。高市早苗氏の提言に見られるように、給付偏重から制度転換する余地があります。 note(ノート)
また、約7兆円という規模の中で、ムダ・重複・明確でない事業を精査する必要があります。 - 省庁間調整・縦割り是正を徹底
幼稚園・認定こども園・保育・学童・障害児支援・家庭支援といった複数省庁をまたぐ領域において、こども家庭庁が「司令塔・調整役」として確実に機能する体制を強化する。縦割り行政による無駄・制度抜けを防止することが、設立趣旨でもありました。 - 政権交代・高市内閣下での機関再検討を慎重に
高市政権で「庁廃止・統合」といった議論が出る可能性がありますが、むやみに廃止に動くのではなく、まずは「見直し・機能強化」を軸にした再構築案を検討すべきです。支援機能の断絶や国民理解の失墜を防ぐためには、慎重な議論・段階的な改革が求められます。
最終整理表:改革案(存続+改めるべき点)
| 項目 | 現状の課題 | 改革案 |
|---|---|---|
| 会見・説明責任 | 質疑なし・短時間会見など信頼醸成に欠ける | 定例会見+質疑応答・成果指標公表 |
| 予算構成 | 巨額支出だが成果見えにくい・維持支出に偏る | 給付偏重から制度改革型支援へシフト・ムダ削減 |
| 組織機能 | 司令塔機能が十分発揮されていない可能性 | 縦割り省庁調整を強化・部門横断チーム創設 |
| 政権・制度位置づけ | 新設ながら存続意義に疑問の声あり | 高市内閣下でも「存続か廃止か」ではなく「改革強化」を明言 |
| 成果可視化 | 少子化改善などに繋がった実感が薄い | KPI設定・EBPM導入・毎年報告書を公開 |