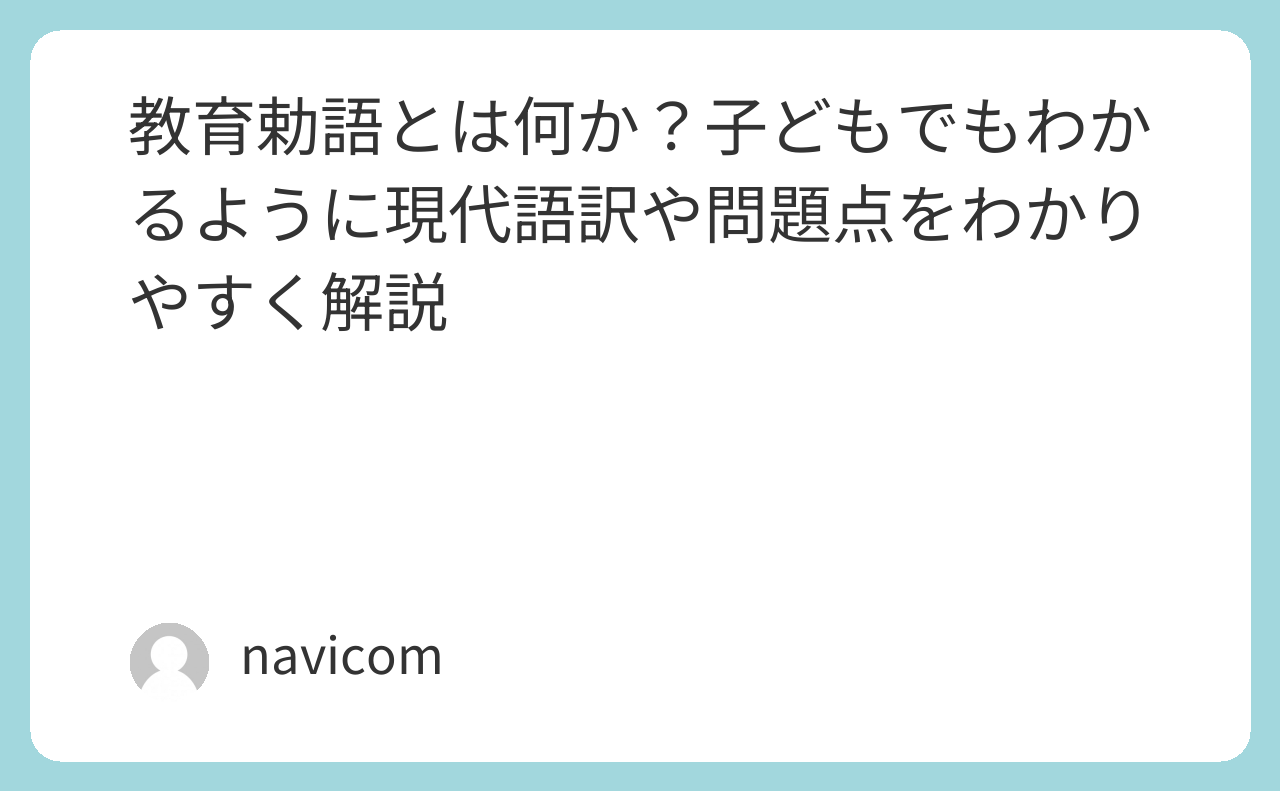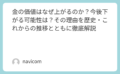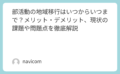- 【第1章】教育勅語とは?簡単にいうとどんなもの?
- 【第2章】教育勅語が生まれた時代背景(明治時代の日本)
- 【第3章】教育勅語の全文と読み方・ひらがな・現代語訳
- 【第4章】教育勅語の「12の徳目」とは?
- 【第5章】教育勅語の良い面と問題点
- 【第6章】教育勅語はなぜ廃止されたのか?(1948年の排除決議)
- 【第7章】現代における教育勅語復活論と政治的議論
- 高市早苗が教育勅語を読むべきだと主張する背景と意図
- 【第8章】教育勅語と教育基本法の違い
- 【第9章】教育勅語は今どう扱われているか?
- 【第10章】教育勅語を子ども向けに言い換えると
- 【第11章】教育勅語に関する主な年表
- 【第12章】教育勅語から学ぶ「教えの使い方」
- 【まとめ】教育勅語とは何か?——過去と向き合い、未来を考える
【第1章】教育勅語とは?簡単にいうとどんなもの?
教育勅語(きょういくちょくご)とは、明治時代に天皇の名で出された「教育の基本となる考え方」を示した文書のことです。
正式には「教育ニ関スル勅語(ちょくご)」といい、1890年(明治23年)10月30日に発布されました。
発布したのは明治天皇。起草に関わったのは、政治家の**井上毅(いのうえこわし)や元田永孚(もとだながざね)**といった学者・官僚たちでした。
当時の日本は、近代国家として西洋に追いつくために、国民の道徳教育の統一が必要とされていました。教育勅語はそのための「心の教科書」のような存在だったのです。
【第2章】教育勅語が生まれた時代背景(明治時代の日本)
📜 明治時代の日本社会
明治政府は、江戸時代までの身分制度を廃止し、西洋化を急速に進めました。鉄道や学校制度が整備され、国民全体に「国家への忠誠」と「家族の調和」を教えることが求められました。
当時のスローガンは「富国強兵」。国を豊かにし、軍を強くするためには、国民が一体となる「精神的支柱」が必要でした。
教育勅語はその役割を担ったのです。
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1868年 | 明治維新 |
| 1872年 | 学制発布(全国に学校制度ができる) |
| 1889年 | 大日本帝国憲法公布 |
| 1890年 | 教育勅語発布 |
| 1904年 | 日露戦争 |
【第3章】教育勅語の全文と読み方・ひらがな・現代語訳
🔸教育勅語の冒頭(原文)
朕惟(おも)ふに、我が皇祖皇宗、国を肇(はじ)むること宏遠に…
このように古い言葉で書かれており、漢文体です。全文は約315文字。
当時の小学生はこれを**暗唱(あんしょう)**することが求められ、学校では奉読式(天皇の言葉を拝読する儀式)が行われていました。
🈁 現代語訳(やさしく要約)
「私は思います。日本の国は先祖代々が努力して作り上げてきた素晴らしい国です。
国民は父母を敬い、兄弟仲良くし、夫婦が助け合い、友だちを信じ、学び働き、国のためにつくしましょう。
もし国が危機にあれば、命をかけて国を守りましょう。そうすれば天皇の治める国は永遠に栄えるでしょう。」
つまり「家庭を大事にし、社会に尽くし、国家を守る」という道徳の教えです。
【第4章】教育勅語の「12の徳目」とは?
教育勅語には、以下のような**12の徳目(とくもく)**が含まれています。
| 徳目 | 意味(やさしく) |
|---|---|
| ①孝行 | 親を大切にすること |
| ②友愛 | 兄弟や友人と仲良くすること |
| ③夫婦相和 | 夫婦で助け合うこと |
| ④朋友相信 | 友達を信じること |
| ⑤謙遜 | へりくだり、礼儀を守ること |
| ⑥博愛 | 人を広く愛すること |
| ⑦修学習業 | 学問や仕事に励むこと |
| ⑧智能啓発 | 知恵を育てること |
| ⑨徳器成就 | 人格を磨くこと |
| ⑩公益世務 | 社会に尽くすこと |
| ⑪遵法 | 法を守ること |
| ⑫一旦緩急あれば義勇公に奉ずる | 国が危機にあるとき、勇気をもって尽くすこと |
【第5章】教育勅語の良い面と問題点
💡良い面(肯定的評価)
- 家族を大切にする精神や思いやりなど、普遍的な道徳が含まれている
- 社会の秩序を保つ意識を育てた
- 当時の教育現場では、道徳教育の基礎となった
⚠️問題点(否定的評価)
- 「天皇への忠誠」「国のために命を捧げる」という思想が戦争を正当化する方向に使われた
- 国家中心の価値観で、個人の自由や多様性が尊重されない
- 憲法や教育基本法の理念(人権・民主主義)と相容れない
【第6章】教育勅語はなぜ廃止されたのか?(1948年の排除決議)
第二次世界大戦後、日本は連合国の占領下に置かれました。
1947年に日本国憲法が施行され、国民主権・基本的人権・平和主義が定められます。
これにより、教育勅語の「天皇中心・忠君愛国」の考え方は、新しい憲法の理念と矛盾するものとされました。
そのため、1948年(昭和23年)6月19日に、衆議院と参議院の両院で
「教育勅語等排除に関する決議」が可決され、正式に**失効(しっこう)**しました。
【第7章】現代における教育勅語復活論と政治的議論
🗳️ 参政党や一部保守派の主張
近年、一部の政治家や政党(例:参政党、保守系議員など)が「教育勅語の中には良い道徳がある」として再評価を求めています。
特に「家庭や地域の絆を重んじる」「感謝の心を育てる」といった部分は、現代社会にも通じる価値観です。
🏛️ 2017年の閣議決定
安倍政権下で2017年、「教育勅語の内容を教材として使うこと自体は否定されない」という閣議決定が行われ、議論が再燃しました。
ただし、「憲法や教育基本法に反する形での使用は認められない」と明記されています。
高市早苗が教育勅語を読むべきだと主張する背景と意図
1. 幼少期の刷り込みと価値観の継承
高市早苗は、自らの幼い頃から家庭で教育勅語を繰り返し教えられ、暗唱していた経験を公言しており、これが彼女の保守的価値観の土台になっていると語られています。TBS NEWS DIG+2ウィキペディア+2
そのため、教育勅語を読むべきだという主張は単なる理論ではなく、彼女自身の人生体験と価値の一貫性に根ざした信念とも考えられます。
2. 道徳教育・国家観の復権
高市は、現代社会で「日本人としての道徳」「公徳心」「家族・地域の絆」が失われつつあるという懸念を持っています。国のアイデンティティや文化的伝統を守る力として、教育勅語に含まれる道徳規範を再評価すべきだと主張しています。衆議院+2nipponkaigi.org+2
また日本会議と親和性をもつ発言や団体活動にも関与しており、伝統的価値の復興をめざす運動の文脈の中で、教育勅語を象徴的教材と位置づけているようです。nipponkaigi.org+1
3. 教育再生・精神風土の回復を標榜
高市は、戦後教育改革によって道徳や教養、伝統精神が軽視された時期があったとし、現代の教育を「失われた六十五年」などと表現して、教育再生を訴えています。衆議院+1
その中で、かつて国家の道徳規範として存在した教育勅語を、道徳教育や心の教育の“原点”として再導入すべきだという立場をとることがあります。
4. 政治的カウンターテキストとしての意図
教育勅語を読むべきだと主張することには、現代日本の価値観(個人主義・自由主義・多様性)へのカウンターテキストを提供したいという意図も含まれていると見られます。国家中心・伝統中心の価値を強調する保守派の思想的拠り所として、教育勅語は象徴的な役割を果たします。
さらに、2017年には内閣が「教材としての教育勅語の使用を否定しない」との答弁を認める方針が示され(ただし憲法・教育基本法との整合性前提)、政治的議論の場でも取り上げられるようになりました。人民網+2Facebook+2
このような政治潮流の中で、高市の主張は政策実現を見据えた発言でもあり、保守層に訴えかける戦略の一部とも解釈できます。
5. リスクと批判への意図的な挑戦
教育勅語復権主張には批判も多く、「国家主義・天皇中心主義への回帰」「歴史修正主義の懸念」などが指摘されます。高市があえてこの主張を公言することで、保守派の支持を固めると同時に、批判を受ける立場をも取る挑戦的姿勢を示しているとの見方もできます。
【第8章】教育勅語と教育基本法の違い
| 比較項目 | 教育勅語(1890) | 教育基本法(1947) |
|---|---|---|
| 発布者 | 明治天皇 | 国会(法律) |
| 内容 | 道徳・忠君愛国・家族中心 | 個人の尊重・民主主義・平和 |
| 教育の目的 | 国家への奉仕 | 人格の完成と幸福の追求 |
| 価値観 | 上下関係・義務 | 平等・人権・自由 |
教育勅語は「国家のための教育」だったのに対し、教育基本法は「人のための教育」といえます。
【第9章】教育勅語は今どう扱われているか?
現在、教育勅語は法律上の効力はないものの、歴史教育や道徳教育の題材として紹介されることがあります。
また、幼稚園や一部の保守系学校で暗唱を行うケースもあり、賛否が分かれています。
教育勅語を「そのまま教える」ことは問題がありますが、内容を歴史資料として学ぶことには意義があります。
「なぜ当時はこのような考え方が広まったのか?」を理解することが、近代日本を考える第一歩です。
【第10章】教育勅語を子ども向けに言い換えると
「みんなで仲良く、家族を大切にしよう。困っている人を助けよう。国のために働くのも大事だけど、人の命と自由も大切にしよう。」
これが、現代的な「教育勅語のエッセンス」です。
道徳としての価値を学びながらも、「国家のために命をささげる」という危険な思想には注意が必要です。
【第11章】教育勅語に関する主な年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1890年 | 教育勅語発布 |
| 1904年 | 日露戦争、忠君愛国が強調される |
| 1937年 | 日中戦争、軍国教育の中心に |
| 1945年 | 敗戦、日本国憲法制定へ |
| 1948年 | 教育勅語排除決議 |
| 2017年 | 教材としての使用を容認する閣議決定 |
【第12章】教育勅語から学ぶ「教えの使い方」
教育勅語の本質は「時代によって解釈が変わる」という点にあります。
道徳は普遍的な価値を持ちますが、国家がそれを利用するとき、思想の道具になってしまうことがあります。
現代の教育に必要なのは、「誰かに言われたから守る道徳」ではなく、
「自分で考え、選ぶ道徳」です。
【まとめ】教育勅語とは何か?——過去と向き合い、未来を考える
教育勅語は、明治時代の価値観を象徴する歴史的文書です。
その中に「家族愛」「努力」「思いやり」といった良い教えもあれば、
「国家への絶対服従」「個人の犠牲」といった問題点もあります。
私たちが学ぶべきは、「その教えをそのまま信じること」ではなく、
なぜその教えが生まれ、どう使われたのかを知ることです。
歴史を学び、過ちを繰り返さないために、教育勅語は今も私たちに問いかけ続けています。