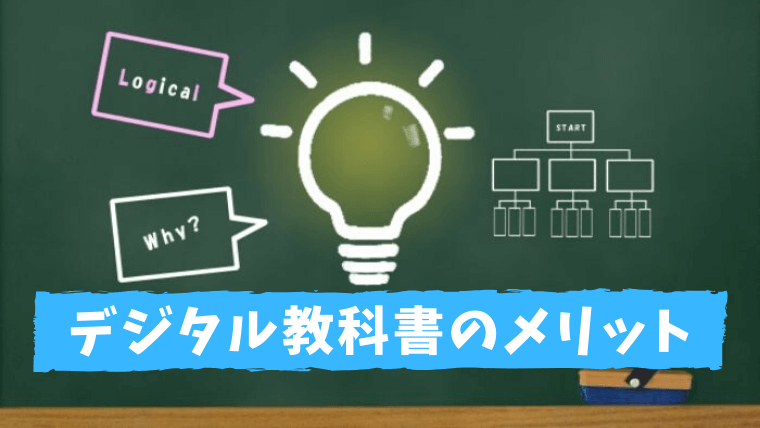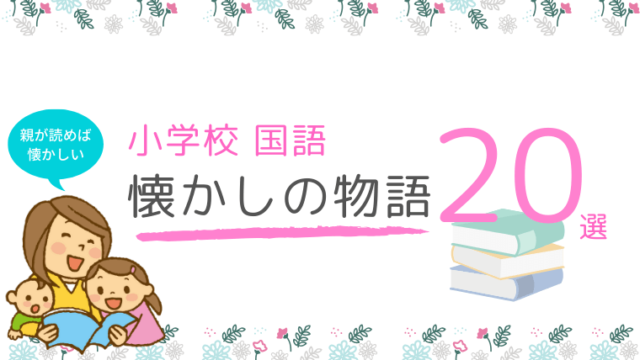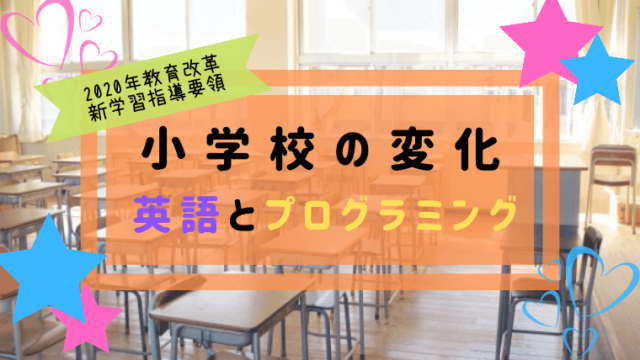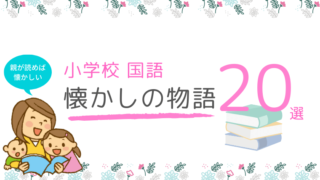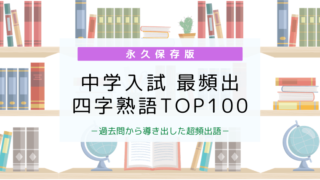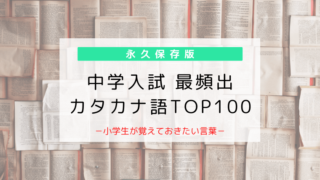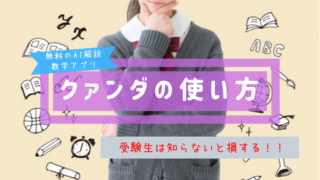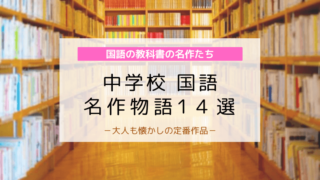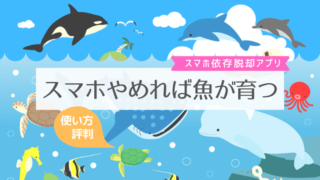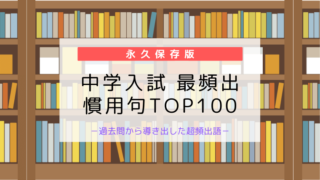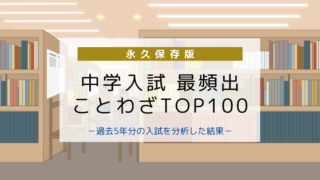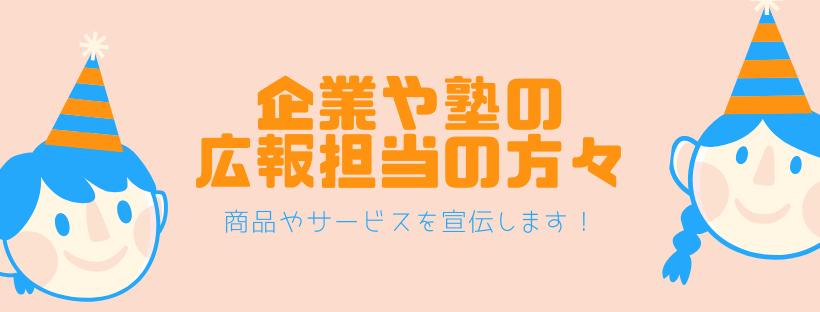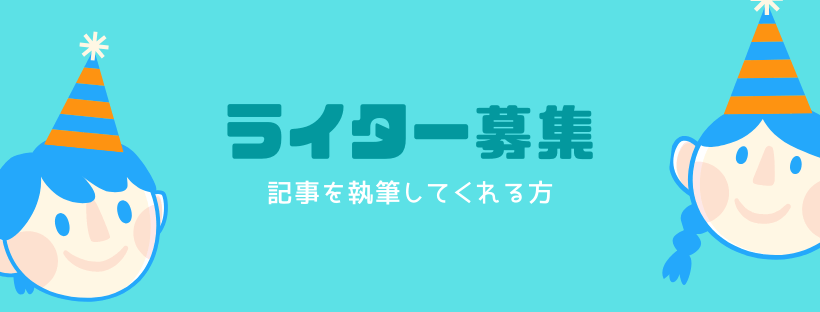紙の教科書に取って代わり、PCやタブレットを利用したデジタル教科書で学校のすべての授業がなされていく未来はもうすぐそこまで迫っているのかもしれません。
デジタル教科書普及の背景
[jin_icon_mail-send]小中学校に一人一台のPC無償配布
[jin_icon_mail-send]小学校プログラミング教育の開始
[jin_icon_mail-send]次世代ネットワーク5Gの普及
日本政府が急速にICT環境の整備を進めていこうとしているのは火を見るよりも明らかであり、なかでも学校教育の場においては、新課程の2020年が大きな変革の年となり得ます。
そこで今回は、今後全国の小中学校でいっそう普及していく可能性が高い「デジタル教科書」について、
デジタル教科書とは何か?
デジタル教科書の効果や課題
デジタル教科書のメリット
デジタル教科書のデメリット
といった小学生のお子様をもつ親が気になるポイントをまとめてみました。
目次
デジタル教科書とは何か


デジタル教科書とは、その名のとおり「紙の教科書の内容がそのままデジタル化されたもの」であり、子どもが使う「学習者用デジタル教科書」と先生が使う「指導者用デジタル教科書」の2種類に分けられます。
学校教育法等が改正されたこともあり、授業のなかで紙の教科書とあわせて使用することが可能になりました。
紙の教科書は文部科学省の検定に合格したものだけが認められているため、デジタル教科書は紙の教科書の内容から変更することなく、そのまま記録されている必要があります。
デジタル教科書の普及率
全国の小中学校のデジタル教科書(指導者用)普及率は、小学校が56.6%、中学校が61.3%であり、約6割程度と進んでいない現状です。
| 全国の学校数 | デジタル教科書あり | 割合 | |
| 小学校 | 19,331校 | 10,936校 | 56.6% |
| 中学校 | 9,325校 | 5,720校 | 61.3% |
| 高等学校 | 3,550校 | 682校 | 19.2% |
(学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果〔確定値〕(平成30年度)より)
紙の教科書は国からの無償配布なのに対して、デジタル教科書は有償であり、都道府県や自治体が予算を取れるかどうかで変わってきます。教育用予算が少ない自治体では、当然デジタル教科書の普及が進まないのです。
PCやタブレットの普及率
2011年からの「教育の情報化ビジョン」や「学びのイノベーション事業」といった文部科学省による教育現場のICT化が進められてきましたが、都道府県や自治体によってPC普及率にも格差が生じている実態があります。
なかでもPCが最も普及している佐賀県は、教育用PC1台あたりの児童生徒数が1.9人と高いのに対して、最下位の愛知県は7.5人とその差が大きく開いています。
デジタル教科書の機能
デジタル教科書には、紙の教科書にはできなかった画期的な機能がたくさんあります。
デジタル教科書の基本機能
・音声や動画の再生機能
・文字やグラフの拡大機能
・データの保存機能
・書き込みや作図機能
・印刷や資料参照機能
デジタル教科書は制作している教科書会社によって特長は異なりますが、およそ上記の基本的な機能を有しており、紙の教科書にはない様々なコンテンツを利用できることから、学習の幅を大きく広げることができます。
デジタル教科書のメリット


デジタル教科書のメリット①「学習の幅が大きく広がる」
デジタル教科書の最大のメリットは、生徒の理解を深めたり発展的な学習をしたりするのに役立つ豊富なコンテンツを利用できるところです。
たとえば、国語の文学作品に描かれている場所の映像を見て、物語や情景について深く想像できたり、算数の図形問題を生徒自らが図形を動かしながら理解できたりするように、様々な学習効果が期待できます。
生徒自らが関心をもったコンテンツや気になったところをPCやタブレットに保存できれば、その後の反復学習やさらなる発展学習にもつなげることができるのです。
デジタル教科書のメリット②「学習管理がしやすい」
紙の教科書との大きな違いとして、デジタル教科書は学習管理がしやすいところが大きなメリットです。
たとえば、自分の苦手な問題傾向がわかったり、解答までにどれくらいの時間がかかったかを把握できたりするなど、学習状況や学習結果を知ることができます。
生徒自身が自分で管理できることはもちろん、教師や保護者も共有できることが大きな特長です。
デジタル教科書のメリット③「誰にもやさしいユニバーサルデザイン」
最近は、学校教育の場においてもユニバーサルデザインが主流となっていますが、デジタル教科書はとくにユニバーサルデザインに優れた機能を持っています。
ユニバーサルデザインとは、国籍や年齢、性別や障害の有無など関係なく、だれにとっても見やすく使いやすいデザインのことをいう。
たとえば、文字や図を好きな大きさに拡大できる機能や見やすい配色に変える機能、白黒反転機能や音声の読み上げ機能などがあります。
デジタル教科書は、すべての人が平等に教育を受けられる機会を実現することができるのです。
デジタル教科書のデメリット
教師の管理負担や管理コストの増加
デジタル教科書のデメリットとしては、学校現場の管理コストが増加することです。
仮にすべての生徒にPCやタブレット端末が一台ずつ配布された場合、それらを管理する責務は学校側が受け持つことになります。
日々のメンテナンスやソフトウェアのアップデート、セキュリティー対応など、紙の教科書とは比べ物にならない管理業務が生じます。
専門的な知識や技術もある程度必要になり、教師の業務負担は増える一方です。
PCやタブレットの無償配布について
2019年12月に政府が「全国の小中学校に生徒一人一台の学習用パソコンまたはタブレット端末を無償で配布する」という方針を固めました。
これについては、「教師の負担が増大する」「PCは数年で買い替えが必要だが予算は継続的にとるのか」といった否定的な意見も聞こえており、教育ICT化には課題が残っています。
次世代高速ネットワークの5Gが2020年から日本国内でも普及していくことやプログラミング教育の開始により、ますます身近なところでICT化は進んでいきますが、
学校教育においては事を急ぎすぎず、確かな将来の見通しをもって教育改革が進んでいくことを望みます。